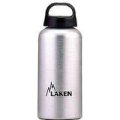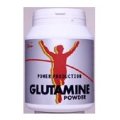B型人間の山歩き ブログ HOME Amazon Yahoo! JAPAN Google
笹子雁ヶ腹摺山
(山梨県大月市他、1357m)
ウェザーニュース:大月 Yahoo!大月市の天気 山と高原地図:大菩薩嶺 富士急山梨バス 日帰りトレッキングの服装
冬の里山トレッキングの装備と服装 日帰り登山、ハイキングの持ち物・道具チェックリスト よく行く東京の登山用品店
|
当日のコース |

〜オススメ山グッズ〜
2007年の初登山は、1月14日に、2年生の長男と2人で山梨県の笹子雁ヶ腹摺山(ささごがんがはらすりやま)に行ってきました。
行く前カミさんに言われました。「この寒いのによく山なんか行く気になるわねえ」
はい、行く気満々♪です。お許しがいただければ、なんなら毎週でも私は一向に構いません。私は外遊びが好きなのに加え、近頃はメタボリック対策も兼ねているのです。
それでは当日の日記です。
![]()
国分寺駅6:08発の中央線で八王子まで行き、中央本線に乗り換えて笹子駅まで行きます。
JRの各駅には、今年のNHK大河ドラマの「風林火山」の幟(のぼり)がたくさんはためいていました。この寒い時期にもやはり登山に行く人は結構いて、電車内にはリュックを持った人がちらほら見かけられます。
長男はトンネルが気になるようで数を数えていました。
「もう13本目だよ!」
7:31に笹子駅着。快晴で風もなく、絶好のコンディションです。ただ、電車を降りると思いのほか日陰などに雪が積もっています。
私は革の登山靴だったのですが、長男は普通のスニーカーだったので、「おい、雪の上を歩くと靴が濡れるといけないから雪の上は歩かないようにしろよ」
というと、「うん」と返事をしたのですが、駅前の日陰に雪が積もっているのを見つけると、「わーい!」とすっ飛んでいって、もう雪を踏んづけています。まあ、無理もないのですが・・・
笹子駅は無人駅でした。今日は笹子雁ヶ腹摺山に登ってまたここに戻ってきます。
7:35駅発。
笹子駅から笹子雁ヶ腹摺山登山口までは国道20号(甲州街道)を歩いていきます。標準コースタイムは45分ほどかかるようなのでバスで行けないかと思い富士急山梨バスに問い合わせてみましたが、土日はほとんど便がないとのことで仕方なく歩くことに。
日陰には雪が
30分ほど歩くと笹子鉱泉が現れましたが、すでに廃業らしく、今回は山帰りの温泉はなし・・・
それにしても、性分なのか、見知らぬ道を歩くのはなんでこんなに楽しいというか、ワクワクするのだろう。特に目新しいものがあるわけではなくても、初めて歩く道というのは心沸き立つ気がします。
国道が右に大きくカーブするところで左の旧道に入り、ちょっと行くと笹子雁ヶ腹摺山の登山口があります。
8:30登山口。コンビニ(今はなくなりました)に寄ったら笹子駅から1時間近くかかってしまいました。
登山口の気温は1度。今回は真冬の登山ということでどのくらい寒いのか調べたく、温度計を持ってきました。温度計つきデジタル腕時計などという文明の利器はないので、家庭用の温度計(直径14cm、湿度計つき)を持参しました。
気温というのは100m標高が上がるごとに0.6度下がると言われていて、登山口が標高約600mだとすると、標高1357mの笹子雁ヶ腹摺山山頂とは750mほど差があるので、0.6×0.75=0.45、つまり4〜5度くらいは低いことが予想されます。
さらに風が強い場合には体感温度はもっと下がるので、そこからさらに−5〜−10度はありうることを覚悟はしていました。そのため、防寒は2人ともバッチリしてきました。
しかし、長男の靴は・・・
登山口から歩いてすぐに樹林帯に入りますが、「ここ」という登山道がなくなり「むむむ!?」と思いましたが、適当に登っていくとやがて登山道が現れました。
南側に面した斜面だからなのか、空気が乾燥しているからなのか、カラッとした山の空気がとても爽やかで心地よかったです。
マニアックな山で交通の便も決してよいとは言えない山なので、今回はもしかしたら他には誰もいないかもしれないなあと思っていました。ところがどっこい意外に多くの登山者がいて、(アンタも好きねえ・・・)と心の中でつぶやいてしまいました。
雪はまばらにありますが、初めのうちは登山道にはありませんでした。
ところが標高も上がってくると、ご覧の通りの雪道に。昨年の今頃行った近隣の百蔵山にはほとんど雪がなかったので、今回も大丈夫だろうとタカをくくってしまったのがいけませんでした。
「おい;靴が濡れるからなるべく雪のないところを歩いてくれって;」
長男はメッシュ地のスニーカーで来てしまったもので、靴が濡れて冷たくないかちょくちょく確認しながら歩きました。
「大丈夫だよ。冷たくないよ」
右写真が笹子雁ヶ腹摺山。無地の看板が目印です。
そもそもなんで今回この山に目をつけたかというと、中央高速で東京から山梨方面に行くときに通る「笹子トンネル」の上の山で、気になっていたからです。普通の人はそんなこと気にならないですか?
笹子雁ヶ腹摺山の下には中央高速とJR中央本線の笹子トンネル、国道20号線の新笹子トンネルが通っています。
JRの笹子トンネル(全長 4,656m)は1902年(明治35年)に完成し、1931年(昭和6年)に上越線清水トンネル(総延長9,702m)が完成するまで、日本一の長さを誇るトンネルだったそうです。
また、山梨方面に車で行楽に出かけると、東京方面に中央高速で戻るときはまずこの笹子トンネルで小渋滞があり、それから小仏トンネルの大渋滞に巻き込まれるのが定番です。
凍っているところもありますが、注意して歩けば問題なかったです。
寒さを警戒してこの山行前日にユニクロでダウンジャケットを買ってきて、それを着て歩いていましたが、雪のある山でも暑い暑い;。途中で脱ぎました( ̄O ̄;)
看板が右側に見えたら山頂はすぐそこ!
10:20、無事山頂着。
こちらは北方向の眺め。
南を振り向くと・・・
富士山が上半身を見せてくれます。
さらに西方向には・・・
南アルプスの山並みと、八ヶ岳&甲府盆地の大パノラマが。
穂高連峰もちょこっと見えたし、金峰山の五丈石もちっちゃく見えました。
ここは「笹子」雁ヶ腹摺山ですが、この附近にはほかに雁ヶ腹摺山と、牛奥ノ雁ヶ腹摺山という似たような名前の山があり、旧五百円札の富士山の絵は、雁ヶ腹摺山から見た富士山だそうですね。
そしてここで湯を沸かし、我が家定番のカップラーメンを食べました。
温度計を見ると、気温は0度、湿度42%で、登山口とほとんど変わりませんでした。風はありませんでしたが、じっとしているとやはりだんだん寒くなってきました。
そして、「おい、ここなら誰もいないから思い切りでっかい声出してもいいぞ」と言ったところ、、、
「え〜?・・・
・・・本が水に沈んだよ! ブックブック〜!」
(・・・!? ヤッホーとかじゃないのか; しかし、面白いじゃないか・・・)
予想外の文句にちょっとオドロイてしまいました・・・
1時間ほど経ち、当初は往路を戻るつもりだったのですが、先客の団体が笹子峠方面に下りていったので、まだ時間もあるしちょっと遠回りになるけどいいか、ということで左手の笹子峠方面に下ることに。11:20発。
急坂をゆっくり下りていくと、なんと登りの登山道よりさらに多くの雪が待ち受けていました。
いや〜;まさかこんなに雪があろうとは。山肌にはほどんど雪はないのに、なぜか登山道にはびっちりと雪がついているのです。雪はほとんど固まっていて、踏むと「ザクザク」と乾いた音がします。
「おい;、靴濡れてないか?」と聞くと「う〜ん、ちょっと濡れてるかな」
と言うので靴を脱がせてみたら、やはり靴下が湿っています。あちゃ〜、かわいそうにと反省しましたが後の祭り。替えの靴下に履き替えさせてまた歩き始めます。その後も「足冷たくないか?」と確認しながら行きましたが、本人はあまり気にしていない様子でした。
雪道もひと段落したところで笹子雁ヶ腹摺山を振り返ります。
雪どっさり
雪道もゆっくり歩けばアイゼンやストックも別に必要ありませんでしたが、あれば歩きやすいだろうなとは思いました。
標高が下がるにつれて雪も少なくなってきました。
笹子峠12:30。ここで甲斐大和駅方面と、笹子方面に分かれます。
またしばらく雪の登山道を下っていくと、右写真の笹子隧道に出ます。ここは県道212号日影笹子線で夏場は車も通れるようですが、冬場は雪のため通行止めとなっているようです。
中に入ってみたら、天井から地面に届きそうな「つらら」が何本も垂れ下がっていて、長男は興奮していました。私もあんなのを見たのは何年ぶりだろう・・・
ここからもしばらく雪の県道212号日影笹子線を歩いていきます。
踏み跡はたくさんありました
長男は笹子隧道の中で拾ってきた氷の塊を大事そうに持っています。
「おい、手袋が濡れるからもう捨てたら?」
「やだ!家まで持って帰る!」
子供にとってはお宝・・・
雪道もしばらく歩くと雪もなくなってきました。
「おい、電車には氷は持ち込めないぞ」
「う〜ん、そうだね。じゃあしょうがないか」
またしばらく歩くと、矢立の杉入口に。
車道からまた矢立の杉方面の山道に入って数分歩くと、矢立の杉がありました。
先客のおじさんに「その木の中に入ると、空が見えるよ」と言われたので入ってみたら、ホントに中が空洞になっていて空がぽっかりと見えました。でも、ということはこの木も結構痛んでるってことだよなあ・・・
矢立の杉を後に5分ほど歩いたところで長男が、「あっ!木のところに帽子置いてきちゃった!」とヌカスではないですか。
なにい;〜! じゃあここで待ってろよ、と荷物を置いて矢立の杉までひとっ走り。戻ってくると長男が私のザックなどを持って戻って来るところでした。
「だって寂しかったんだもん・・・」
天気もよかったし、やっぱり緑は気持ちいいです
2:15、ぐるっと笹子雁ヶ腹摺山を登って登山口に戻ってきました。
そしてまた車道を歩き、3時ちょうどに笹子駅着。
ゴ〜〜〜〜ル!
やはり関東は冬場の山歩きも快適にできていいなあと改めて思いました。私の田舎の新潟はこの時期は雪に閉ざされて何もできなくなってしまうものですから。
ただ、想定外の雪には驚きました。長男もなんとか歩き通せましたが、冬場は子供も靴はしっかりとしたものが必要なんだと反省いたしました。
まとめの一句:
冬晴れの 雪を踏む音 峠道
近くの山 : ・九鬼山 ・高川山 ・百蔵山 ![]() ・岩殿山 ・雁ヶ腹摺山
・岩殿山 ・雁ヶ腹摺山
B型人間の山歩き 雁ヶ腹摺山登山日記
冬の里山トレッキングの装備と服装 日帰り登山、ハイキングの持ち物 日帰りトレッキングの服装
ザックのメーカーリスト シューズのメーカー ![]() 雨具のメーカー トレッキングポールのメーカー トレッキングパンツのメーカー
雨具のメーカー トレッキングポールのメーカー トレッキングパンツのメーカー
Copyright(c) B・Y.All rights reserved. プライバシーポリシー