|
 
登山靴
amazon.co.jp
登山靴
トレッキングシューズ
ハイキングシューズ

くつひも
|
登山用品の三種の神器の第一は、登山靴(トレッキングシューズ)。まずは足元を固めましょう。ちょっとしたハイキング程度ならスニーカーでも大丈夫なんですが、やはり山登りに行くならちゃんとした登山靴のほうが安心感があります。
登山靴のメリットは、作りがしっかりしていて足の保護性能が高いこと、防水性が高いこと、靴底に深い溝があって滑りにくいこと、などでしょうか。
以前、ちょっとした登山コースをミュールで歩いていたお姉さんを見かけたことがあります(こちらの日記)が、ケガの元ですから、無謀なことはやめましょう。
登山靴のサイズの合わせ方のメドとしては、厚めの登山用の靴下などをはいて、足のつま先をトントン!と突いて足先を靴のつま先に着けた状態で、足の後ろのかかとの部分に指1本入るくらいであれば大丈夫だと思います。普段はいている靴プラス1cmがメドでしょうか。
ただ、同じサイズの靴でも、メーカーによりクセがあって、幅広だったり幅が狭かったりします。とにかくはいてみて、違和感を感じるようならやめたほうがいいでしょう。とは言っても、はいているうちになじんでも来ますので、そのあたりはやはりお店の人と相談するのが一番です。合わない靴をはくことほど苦痛なことはないですから、納得いくまで検討しましょう。履き慣れないうちは靴ズレになってしまうこともあるので、絆創膏を携行するといいですね。
なお、靴紐は、登りはゆるめでもよいが、下りはしっかりと締めたほうがいいとも言われています。靴紐の予備も持っていったほうがいいと、登山入門などには書いてありますね。用意しておけば安心です。私も一応ザックにしのばせています。
ちなみに私が現在無雪の山で愛用しているのは、スポルティバのシンセシスGTXサラウンド(グレイグリーン) 楽天。
・登山靴・トレッキングシューズのメーカーリストはこちら
・ネットで人気、クチコミの多い登山靴まとめ
・山歩き用ローカットシューズのブランドとシリーズまとめ
|
|

ザック
・デイパック
|
登山用品の三種の神器の第二はザック(リュックサック)。日帰りなら20~30リットル程度の容量のデイパックでも対応できるかと思います。ザックには個性的な収納機能や、背面・側面から内部の取り出しができるものなどもあります。まあ自分の好みのデザインのものを、懐具合に応じて選べばいいでしょう。しかし、カッコいいザックはやはり値が張るように感じるのは、メーカーもよく考えてるってことですかね。
なお、「ザックカバー 」という用具も売られてはいますが、要はザックの中身が濡れなければよいわけで、ザックの中に入れるものを濡れないようにビニール袋に入れるなどすれば、ザックカバーというものはいらないようにも思います。まぁ日帰りならなくてもなんとかなると思いますが、泊まりでの山行となるとあった方が安心ですね。ザックカバーつきのザックもあります。 」という用具も売られてはいますが、要はザックの中身が濡れなければよいわけで、ザックの中に入れるものを濡れないようにビニール袋に入れるなどすれば、ザックカバーというものはいらないようにも思います。まぁ日帰りならなくてもなんとかなると思いますが、泊まりでの山行となるとあった方が安心ですね。ザックカバーつきのザックもあります。 |

ザックカバー
|
私が現在使っている日帰り用のザックはノースフェイスのカイルスの28リッター。色はスレートグレーです。色味が他にない感じで気に入っています。 楽天
・登山・トレッキング用ザック、リュックのメーカーと選び方
・子供用リュックサック・デイパックのメーカーリスト
|
|

雨具
|
登山用品の三種の神器の第三は雨具(レインウェア)。山登りに行くときの必須アイテムです。この雨具をコンビニや100円ショップの安物ポンチョなんかでケチろうとすると、痛い目に遭いかねませんのでご注意を。
ゴアテックスが主流ですが、今は素材も様々あって品質も向上しているようです。上下で1万円程度以上のものなら十分かと思いますが、値段の張るものはそれなりの着心地や防水性の強度などが期待できるかもしれません。
山歩きで雨具を着込むハメになったのは槇寄山、酉谷山、雲ノ平。
ちなみに私が2004年から使い続けている雨具は、モンベルのレインダンサー。 楽天
・登山・トレッキング用雨具のメーカーリストはこちら
|
|
|
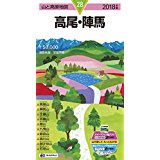
登山地図

マップケース
楽天 |
山登りに行くときゃ必ず持って行きましょう。これも重要な登山用品のひとつです。普通の登山者が行くようなメジャーな山なら、たいてい昭文社の山と高原地図でカバーしているはずですが、地方の山などは人気の山でも出てないことも多いでしょう。とにかく何かしら地図は持って行きましょう。ついでながら、地図はコンパスとセットです。これは絶対です。
地図を見るために、マップケースに入れて首から下げる手もあります。ちなみに私は長い間マップケースは使わずウエストポーチに入れて出し入れしていましたが、やたらと折り畳んだり広げたりするので、すぐに地図が傷んでしまうのでした。マップケースに入れておけば見やすいですし、傷んだりすることも少ないでしょう。コンパスも一緒に入れておくと方向も確認しやすいです。初めてマップケースを使ったのは乾徳山。私が使っているのはシートゥーサミットのSサイズ。
今はiPhoneなどのスマホでも左記の山と高原地図が見られるアプリもありますし、グーグルマップをはじめとするネットのサービスの地図もスマホで見ることができて便利です。ただ、スマホの地図サービス(グーグルマップ、ヤフー地図など)が使えるのは、あくまでケータイの電波が届く範囲内でのこと。圏外になったらアウトです(有料の地図アプリなどは圏外でも使えたりしますが)。それに、スマホというヤツはバッテリーの消耗が激しいです。肝心なところでバッテリー切れなんてことになったら大変です。やはり、アナログ的な紙の地図は必要だと思います。
ちなみに、昭文社の山と高原地図における難路(破線路)を歩いていて道迷いしてしまったのは、群馬の鹿岳(かなたけ)。
 私が作った昭文社の山と高原地図リストはこちらです。 私が作った昭文社の山と高原地図リストはこちらです。
|
|

コンパス
楽天
|
地図と合わせて必ず持っていかなければならない登山道具がコンパス。やっぱりこれがないと不安です。というか、地図とコンパスを持って行くのは登山者の義務です、ハイ。100円ショップなんかでも売ってたりしますが、ちゃんとしたものを用意したいですね。
里山のハイキングで道迷いに遭い、コンパスが活躍したのは神奈川の峰山。
群馬の鹿岳から木々岩峠方面に破線ルート(やや難路)を行ったときも道迷いをし、やはりコンパスが活躍しました。
ちなみに、コンパスを忘れちゃった山行記は東京の市道山~臼杵山と、酉谷山避難小屋に泊まる山旅のときです。こういうときに限って、登山道が怪しくなります。
|

水筒

山専用ボトル |
まあ今どきはペットボトルをそのまま持っていけば用が足りるわけですが、ちゃんとした登山グッズとしての水筒も各メーカーから数多く出ています。夏場の保冷、冬場の保温にはやはりちゃんとしたステンレスの水筒(テルモス)がいりますね。テルモスの定番は山専用ボトル。
|
私が愛用している水筒は右写真のプラティパスの2.5Lのもの。夏山に行くときは、これをカチンカチンに凍らせて持って行くことも。すると、山でキンキンに冷えた水を飲むことができてもうサイコーです。水が減った分は体積が減りますし、コンパクトさもグーですね。
私は日帰りで山に行くときはペットボトル2本と、このプラティパスを持っていきます。毎度水は余りますが、安心感には変えられません。
夏場はテルモスの山専用ボトルに氷をギチギチに詰めて持って行き、飲み物を適宜入れて飲んだりもします。夏は冷たいものが何よりのご馳走ですので。冬は暖かいものを入れていくのもいいです。
|

プラティパス
|
 登山・トレッキング用水筒のメーカーリストはこちら。 登山・トレッキング用水筒のメーカーリストはこちら。
 登山・トレッキングに行くとき、どれくらい水を持って行けばよいか? 登山・トレッキングに行くとき、どれくらい水を持って行けばよいか?
|

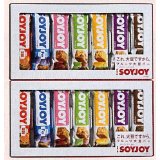
食料・おやつ・
箸・食器類
|
私の日帰り登山・ハイキングの定番の食べ物:
食事・・・コンビニのおにぎり、チキン、ウィダーインゼリーなどのドリンクゼリー。時間に余裕のあるときなどはカップラーメンも。おにぎりを車に置き忘れた山行記は、木曽駒ケ岳と、笠取山。
おやつ・・・小袋入りのせんべい、SOYJOY、カロリーメイト、一口ようかんなどをよく持って行きます。お菓子を買うのを忘れたのは、棒ノ折山。私が小学生のとき、遠足のおやつは300円まででした。
カロリーメイトなどの非常食は残っちゃってもまた後で食べられるものですし、ちょっと余計めに持っていったほうが安心できます。
女性はフルーツを持っていく人も多いですね。
|
|

インソール
|
登山・ハイキングに行って、足の裏が痛くなった経験をお持ちの方はいらっしゃいませんか?そういう人は、足の指でものをつかむ力が弱まっているために痛くなるという話を聞いたことがあります。
このような症状を改善するための運動として、タオルを床に置いて足の指でたぐり寄せるというような方法もよく紹介されています。
しかし、そのようなマメな努力をしている時間や根性のない人には、登山用のインソールを使うことをオススメします。
足の裏が痛くなる場合、インソールにおいて重要なのは、土ふまずの部分にアーチを作ってあげるようなものが有効だということです。まあ個人差もあると思いますが。
私はそのようなインソールを使うようになってから、足の裏が痛くなることはなくなりました。
足裏が痛くて難儀したのは奥穂高岳。
私が長年愛用しているのはコンフォーマブル マルチプラスのMサイズ。
|
|

登山用靴下
|
昔は2枚重ねで履いたりもしましたが、今は専用の厚手の靴下が充実してますし、疲れにくい高機能のものもありますね。
・登山用ソックスのメーカーリストのページ
|
|

ウエストバッグ
|
山歩きにあると便利な用具が、ウエストポーチ(ウエストバッグ)。かつて、登山家の今井通子大先生と一緒に高尾山を登るイベントがあったときに今井さんもそうおっしゃっていて、とっても大きいウエストポーチをお使いでした。
私がウエストポーチに入れているのは、登山地図、メモ帳とペン、コンパス、デジカメ、お菓子類、ティッシュ、緊急用の笛、バンダナなどです。なにかと持ち物が多くなりますが、特に登山地図とデジカメとメモ帳はよく出し入れするので、やっぱりウエストポーチは欠かせません。
特にブランドにこだわらなくても安いもので十分だと思います(私はそうです)が、まあそこは趣味の持ち物なので、好みのものを選びましょう。
・ウエストポーチ・ウエストバッグのメーカーリストはこちら
|
|

 トレッキングポール トレッキングポール
ストック
|
ストック(トレッキングポール)は私にとって欠かせない装備品です。登りでも下りでも、軟弱な私の手となり足となってくれます。やっぱりあると楽ですよ。もちろん、手を使って歩かなければならないような岩場、クサリ場などではしまいますが。
私はI字のタイプのストックを両手に持つダブルストックスタイルですが、T字型のステッキタイプのものを1本持つ人も多く見かけますね。好みの問題です。
ステッキだと、手首を「グキッ!」とやってしまうこともあると聞いたこともありますが、まあ頼り過ぎないように気をつけていれば大丈夫でしょう。
私はストックの石突きで登山道などを痛めないように、先端のカバーは常時つけるようにしています。
登山初心者の方、日頃運動不足の方や体力に自信のない方にはぜひおすすめしたい登山用品です。
初めてストックを使ったのは、赤城山。
私が長年愛用しているのはブラックダイヤモンドのウルトラディスタンス。 楽天
登山用ストック、ステッキ、トレッキングポールのメーカーリストはこちら。
|
|

帽子 |
日差しをさえぎったり頭の防護になる帽子は登山に欠かせないアイテムです。
主なタイプとしてはつばのあるキャップと左画像のハットがありますが、ハットをかぶる人の方が多いような印象があります。
私が現在愛用しているのはナコタの2WAYアクティビティハット。 楽天
帽子を忘れちゃった山行記は越後駒ケ岳です。
|
|

バンダナ、タオル
楽天
|
汗っかきの方には、バンダナもいいアイテムです。バンダナをハチマキにすると汗が顔に垂れて来にくくなります。
タオルマフラーなんていうしゃれたアイテムもありますね。中尾彬みたいにねじり巻きしてみますか。
|
|

手袋
|
岩場やクサリ場、ロープが連続するようなところでの手の保護、また、寒いときにもなくてはならないのが手袋。私は基本的にいつでも手袋はしています。別に軍手でもいいんですが、専用のトレッキンググローブなどはやはりスマートな感じがしますね。
手袋が活躍したのは北穂高岳~奥穂高岳、五竜岳~鹿島槍ヶ岳、二子山、乾徳山、
御前ヶ遊窟。
 登山用手袋・トレッキンググローブのメーカーリスト 冬用手袋 スマホ用手袋 登山用手袋・トレッキンググローブのメーカーリスト 冬用手袋 スマホ用手袋
|
|

ヒザサポーター
楽天
|
山の下り坂でヒザがガクガクして、足が「生まれたての子鹿」のようになってしまう人はいませんか?
そんな方は、トレッキング用のヒザサポーターを装備してみることをオススメします。このサポート感は素晴らしいものです。特に、下山時に効力を発揮しますね。
私が日帰りの山歩きで使っているのは、ザムストのこちらのもの。大事な登山道具(下山道具?)です。ヒザのガクガクが軽減されますよ。初めてヒザサポーターを使ったのは、山梨の権現山。
ただ、私自身は現在では次項目のサポートタイツを愛用しています。
ヒザサポーターとサポートタイツの違いは、やはりサポートタイツの方が脚全体をサポートする分、スムーズな足運びをサポートしてくれるような気はします。個人的な感想ですが。
|

サポートタイツ |
今は山でも着用している人をよく見かけますね。長ズボンの下に履いてももちろんOKですが、お好みのショートパンツ、山スカートなどと合わせたスタイルでオシャレ感を楽しむのもいいですね。
私はかつて、コースタイムが5、6時間程度以上になりそうなときに着用するようにしていましたが、今ではちょっとした日帰りの山歩きでも着用しています。
私は長時間の山歩きとなるとヒザが痛くなってしまうのですが、このサポートタイツのサポート感は素晴らしいものがあります。ヒザはガクガクしませんし、疲労や痛みも軽減してくれます。ヒザのスムーズな動きをサポートしてくれているのだと思います。サポートタイツを使用するようになってから、山歩きでヒザがおかしくなることが無くなりました。
ちなみに私はワコールのCW-Xのロングタイプで、クールマックスという素材を使った、前開き(これがトイレ時に便利)タイプのものを使っています。
初めてサポートタイツを使用したのは東京の川苔山。
・サポートタイツのメーカーリストのページはこちら
ちなみに、ヒザサポーターとサポートタイツを同時に着用したら最強なのではないか?と思い、やってみたことがあります(東京都三頭山)。
しかし、かえって歩きづらかったです。やはりどちらか一つで十分でしょう~
|

スパッツ(ゲイター) |
登山用品の中でも定番の装備品。ぬかるんだ登山道の泥除け、小石や木屑や雪などが入らないように、スパッツ(ゲイター)が活躍します。
私は長ズボンのときは使わないのですが、ショートパンツ+サポートタイツのときは、ショートスパッツやレッグカバー(薄手、短めのレッグウォーマー)を使います。 |
|

ヘッドライト
楽天
|
山用語ではヘッデンと言いますね。早朝の山歩き、暗い山小屋での懐中電灯代わりなどに使えます。山歩きが夜遅くなってヘッドライトのお世話になるということはないようにしたいものです。私は何でも早め早めをモットーに行動するので、毎度持っては行きますが夕刻の山歩きの灯りとしてはまだ一度もお世話になったことはありません。
今はLEDが主流ですね。昔の電球より強力で、明るさも増していていいですね。
私が現在使っているのはブラックダイヤモンドのコズモ。ワンビーム、ツービーム、ツービーム点滅、赤色灯の、4種の光を使い分けることができます。もちろん夜道歩きでも明るさは十分です。
|

救急用品
(ファーストエイドキット)
楽天 |
絆創膏はちょっとしたケガのほか、靴ズレで傷んだ足の保護にも使えるので、必ず持参しましょう。その他、消毒薬、ガーゼ、テープ、ハサミ、湿布、筋肉痛緩和剤、痛み止め(バファリン等)くらいは常時持っています。山の途中で湿布のお世話になったのは、奥穂高岳、十二ヶ岳。
あと、山歩きの途中でひざの痛みが激しく、歩くのも辛いようになったら、右写真のようにひざを軽く曲げ、包帯やテーピングテープをひざの上下にグルグルと多少きつめに巻きます。ひざのお皿が動かないように固定する感じです。こうして、ひざをあまり曲げないようにして歩くと、痛みを軽減できます。万が一の時はお試しください。これで助かったのは槍ヶ岳に行ったとき(その日の日記)。 |
|

ひざが痛くてどうしようもないときは、このように包帯やテーピングでちょっときつめにひざを固定すると痛みを軽減できます。 |
|
|

緊急ホイッスル
楽天
|
笛は山で何に使うのか?交通整理をするためでも、鷹を呼ぶためでもありません。
例えば、一人の山行で足をすべらせて崖から落ちてしまったとします。
そこは谷底で、救援の声を出そうにも届きそうにありません。大声を出し続けるのは疲れますし、体のどこかを骨折でもしていようものなら、声すら出せないかもしれません。
そうした緊急時でも、笛を吹くことくらいならなんとかできるのではないでしょうか。高い笛の音は、自分を探しに来てくれた人へのアピールとなってくれるはずです。また、単に道迷いや遭難しかかって助けを呼びたいときにも、声を出し続けるよりは笛のほうが楽に音を出すことができるはずです。
仲間とはぐれてしまったときや、離れたところにいる仲間への合図などにも使えるでしょう。仲間と山に行くときは、メンバーの笛の音を確認し合っておくといいかもしれません。また、連絡のときは「ピーピー」と2回吹くとか、ルールを決めておくとなお良いでしょう。
「熊出没注意!」などという看板のあるところでは、熊よけ鈴に加え、笛も吹くのも効果が望めるでしょう。
私は幸いにこれまで一度も笛を吹いたことはないのですが、お守り代わりにいつもウェストポーチにしのばせてあります。
|
|

熊よけ鈴 |
山に出かけるときに、熊よけ鈴を鳴らして歩く人もちらほら見られます。熊は人間がいるのがわかれば近づいて来ないそうです。ですから、何か音を鳴らして歩いていれば、向こうから離れてくれるらしいです。鳴らす音は熊よけ鈴のほか、ラジオ、音楽、ホイッスルなどなんでも構わないそうです。
かつて、登山家の山野井泰史さんが、在住している東京の奥多摩の山で熊に襲われて怪我をしたという事故もありました。東京ですら熊がいるんです。持って行くに越したことはないと思います。
季節としては、やはり秋の冬眠前には人里に近いところに熊が出没する傾向が見られるようなので、秋の山行には携行したいところですね。
山の行き帰りの電車の中などでは外しましょう。街に帰って来ても、たまに外すのを忘れてる人に会うことがあります。
万一熊と遭遇してしまったら、「背を向けて逃げない」のが大切だとよく言われますね。熊は逃げるものを追う習性があるそうで、向こうは山の中で暮らしてますから、ものすごいスピードで追いかけてくるらしいです。熊の方を見て、ゆっくりと後退するのがいいとのことです。ただ、私自身は情報として知っているだけで、実際体験したことはないのですが。遠目ですら山で熊を見たことがありません。なるべくならお会いしたくないですね、お互いのために(笑)
「熊出没注意!」の看板があったのに熊よけ鈴を持っていかなかったのは東京・奥多摩の御前山。
 熊よけ鈴、ベアベルのメーカーリストのページはこちらです。 熊よけ鈴、ベアベルのメーカーリストのページはこちらです。
|

登山用腕時計 |
コンパスつき、高度計つき、気圧計つき、温度計つきなど、いろんな機能のついたトレッキング用の時計も今はたくさんありますね。私はなーんにも機能のないアナログの時計をしているのですが、せめて温度計つきの腕時計はほしいなぁとは思っています。
ケータイにも時計はあるのでなくてもいいといえばいいのですが、まあ普通は持って行きますね。
腕時計を忘れちゃった山行記は日光白根山(無人小屋泊)です。
・登山・トレッキング用腕時計のメーカーリストはこちら
|
|


携帯電話・スマホ
と予備電源
楽天
|
今どきケータイやスマホを持たずに出かける人もいないと思いますが、時計やらメモ帳代わりやらカメラなどその他もろもろ便利な道具には違いないので忘れずに。
山の中では、特に使わないようであれば無駄な電気を使わないように主電源を切っておく方がよいでしょう。電波の弱いところでは、電波を拾おうとして電池を消耗してしまうからです。特にスマホは電池の消耗も激しいですからね。
スマホはGPS付きで、地図サービスなどで位置確認もできますが、それはケータイの電波が届く範囲でのこと。圏外になればスマホで位置確認はできません。現在は圏外でも使えるアプリなどのサービスもありますが、私は利用していません。
スマホ・ケータイは電池が切れてしまえば役に立ちません。予備の電池、電源(モバイルバッテリー)は必ず持って行くようにしたいものです。
ちなみに、最近流行のアイテムとしてセルカ棒を使う若い人も見かけます。自撮りが簡単にできるアイテムです。私はまだ持っていませんが、そのうち買ってしまうかもしれません。 〔楽天:モバイルバッテリー、セルカ棒〕 |
|
着替え、タオル等
(登山の服装ページ)
|
冬など寒い時期は、重ね着用に服を持っていくと思います。そのほかに、着替え用の下着や靴下、フリース、タオルなどは、絶対濡れないようにビニール袋や防水のスタッフバッグなどに入れて持って行くか、もしくはザックカバーを持って行き、雨に備えましょう。万一雨で濡れてしまったときに、着替える下着や衣服、乾いたタオルがあると助かるものです。
登山・ハイキングの持ち物と服装チェックリストのページはこちらです。
|

スタッフバッグ
|
濡れては困る衣類や電気製品類などもろもろは、防水のスタッフバッグに小分けにするのがスマートです。
ビニール袋でも、もちろん問題ありません。ただ、スタッフバッグの利点を申し上げるとすれば、色を使い分けることにより判別がしやすくなること、物を入れてキュッと口を閉じることができたりチャックで閉めることができ、きちんと収納できること、ビニール袋より見た目がスマートであること、などでしょうか。私は今ではスタッフバッグ派です。
 スタッフバッグ・防水バッグのメーカーリストはこちら。 スタッフバッグ・防水バッグのメーカーリストはこちら。 |
|
ペンとメモ帳
|
HP・ブログをやっている私にとって、筆記用具はなくてはならないもの。ふと気づいたことをちょっとメモっておくだけでも、後からよく思い出すことができます。
|
|

トイレットペーパー
|
濡れないようにビニール袋に入れて持って行きます(芯を外してつぶして)。いろんな場面で役に立つので、用意しておくと便利です。ぜひ持って行きましょう。
使ったものは山に捨てず、持って帰りましょう。
|

サバイバルシート |
万が一のビバーク用や、防風用のシートとしても、これがあるとないとではかなり違うと思います。ツェルトというものもありますね。
登山入門書などでは必ず持って行くように書かれている装備品です。私はこれまで幸いにこれのお世話になったことはありませんが、万が一緊急的に山で一晩過ごさなければならない事態になった時には、心強いアイテムになってくれるはずです。
楽天 |
|
ハンカチとティッシュ
|
出かけるときは、忘れずに。
|
|
財布・健康保険証・
免許証など
|
現金がないと往生します。財布以外のところにも現金を分別しておくと保険になります。万一のため、保険証も忘れずに。
|
|

デジカメ
楽天
|
ケータイやスマホで写真が撮れる時代ですが、やはりデジカメはキレイに撮れます。
私が現在使っているデジカメは、ソニーのRX-100M2です
防水じゃなかったデジカメの悲劇の日記はこちら。
「防水デジカメでも悲劇がありうる」という事実の日記はこちら。
|
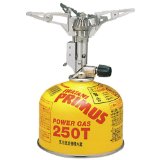
バーナー
と ガス缶

ガスカートリッジホルダー
楽天 |
|
ガス器具を持っていけば、いろいろと食べ物の幅が広がり、リッチな気分が味わえます。山の上でお湯を沸かして食べるカップラーメンは最高ですし、小さな網を持っていって、焼き肉をやったり、もちを焼いたりするのもいいですね。
バーナーには自動点火装置がだいたいついてると思いますが、念のためライターなども持っていったほうがいいと思います。不覚にもバーナーを忘れちゃった山行記は、茅ヶ岳。
また、小型のガスカートリッジを使う場合には、転倒防止のため左画像のガスカートリッジホルダーを利用するのもいいです。
それから、山の上は風が吹いていることも多いです。そんなときに便利なのが、風よけになるウィンドスクリーンです(右写真)。
|

ウインドスクリーン
楽天
|
|
|

クッカー・コッヘル
|
|
ガスバーナーを持って行くなら忘れてならないのはコッヘル(食器)類。私はもっぱらお湯を沸かすのに使ってます。
食事用の箸やフォーク、スプーンなども忘れないように。これらは昔から山用語で武器(ブキ)と言いますね。カトラリーと言ったりもします。
箸を忘れた間抜けな山行記は高川山。さて、どうやってカップラーメンを食べたでしょうか?
|

カトラリー:武器 |
|
|

携帯座布団
|
山頂などで、腰掛けられるところがゴツゴツした岩場しかないなんてこと。また、冬場に座るところが雪の上しかないとか、凍ってるとか、濡れてるとか、そんなときもあります。
そんな場合に座布団の一枚もあると、山の休憩も心地良い気分に浸れますね。
楽天
|
|

ラジオ
|
ラジオを持っていけば、情報入手に重宝することもあります。ラジオを鳴らして歩いているおじさんに時々会いますね。熊よけにもなるでしょう。
新潟の越後駒ケ岳の山小屋で新潟県中部地震に遭ったときには、ラジオの威力をまざまざと感じました。その日記はこちらです。
楽天
|
|

双眼鏡
|
バードウォッチングにもいいですし、遠くの山の山座同定、近くの山、崖に咲く花、同行者の鼻の穴など、いろいろ眺めるのにちょっとしたアクセントとなって楽しいハイキングのお供です。
双眼鏡を持っていったのは、三ツ峠山。
楽天
|

携帯トイレ |
山に行くと、トイレはせいぜい登山口あたりにしかないことが多いです。しかし、山歩きの途中でもよおすことも多いです。
山を汚したくないというエコ意識の高い人には、携帯トイレを持っていくという手もあります。
楽天 |

スポーツ系
ドリンクゼリー |
夏の山歩きはノドが渇きます。そして、暑さとハードな運動のせいで食欲が湧かなくなってしまうこともしばしばです。そんな時にノドの渇きと栄養補給を同時に満たしてくれるのがスポーツ系のドリンクゼリーです。夏山には、ぜひ栄養強力な商品を持って行くことをオススメします。
私は夏場に山に行くときは持って行きますが、毎度一気飲みしてしまいます。 |
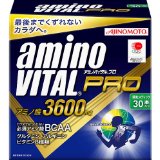
アミノバイタル
楽天 |
|
|

マグカップ
楽天
|
山をお気に入りのマグカップと共に歩くのもいいものです。ザックにくっつけてる人もたまに見かけますね。
右写真は取っ手がカラビナになった、ナチュラルスピリットのマグカップ。
折り畳むことのできるシリコン製カップと言えば、SEA TO SUMMITが定番です。
|

natural spirit
|
|
|

アームカバー
|
「アームカバーなんかするんだったら、長ソデを着てりゃあいいじゃないか」と言う人もいるかもしれません。
半袖シャツにアームカバーをすると脇の下を風が通るため、長袖シャツより涼しく感じらます。また、暑ければ脱いですぐ半袖になれます。そして、スタイリッシュに見える日焼け予防アイテムでもあります。
アームカバーのメーカーリストはこちら
|

フェイスカバー |
女性はフェイスカバーと帽子とサングラスの完全防備で登られる方もお見受けしますね。日焼け予防と美白維持には欠かせないアイテムです。
楽天 |


防虫ネットつきハット |
季節や場所によっては虫が多くてうんざりすることもあるので、防虫ネットを利用するのも手です。防虫ネット付きの帽子もありますし、ネットは単体でも販売されています。
楽天:防虫ネット付き帽子
|

虫除けスプレー |
上記の防虫ネットのほかの虫よけアイテムを使うのもアリです。
山では蜂やアブなどの刺したりする虫の他、やたらとつきまとわれてウザイ虫などに悩まされることもあります。気になる方は虫よけアイテムを利用したり、持って行ったりしましょう。下記のアイテムは登山にも使える、実績のあるものです。虫が嫌いな方はぜひ持って行ってみてください。
私はなぜかあまり登山時に虫に刺された記憶がありません。
(虫も無視するオヤヂ臭?)
楽天:虫よけスプレー、どこでもベープ、富士錦パワー森林香、ハッカ油
|

万能ナイフ
|
私はほとんど使うことはないのですが、仲間とトレッキングに行ったりしてこういう道具が必要になったときに、サッ!と出せるとかっこいい装備品ですね。
楽天
|
|

傘
|
ちょっとした雨降りなら、傘をさすというのもアリかとは思いますが、私はいつも雨具を持ち歩いているので、現在は持っていきません。雲行きの怪しい、軽い散策のときなどは持っていくと安心ですね。
昔、小型超軽量のカサを持って出かけたのは、五竜岳~鹿島槍ヶ岳。
楽天
|
|
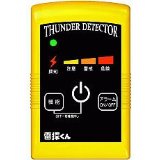
雷検知機
|
雲行きが怪しくなってきて、どうも遠くの方でゴロゴロなっているような気もするけど大丈夫かな・・・?なんて状況になったときに使える道具が雷検知機(雷警報機)。
これが反応し始めたら素早く山小屋に逃げ込む、窪地に逃げる、あるいは下山するなど対策が取りやすくなるでしょう。
山でカミナリ攻撃に遭い怖かった日記はこちら。
海でカミナリという自然の威力をまざまざと感じさせられた日記はこちらです。
|
|

敷き物、レジャーシート
|
ちょっと山や自然の中にハイキングなどに出かけてお弁当を広げてピクニック、というときに欠かせない持ち物がこれ。ベンチや倒木、腰かけられる岩などがないときは必要です。起毛タイプのものなどは安心感がありますね。
楽天
|
|

クーラーバッグ
|
ソフトタイプの軽いクーラーボックスや小型のクーラーボックスであれば、ちょこっと歩きのハイキング、ピクニック程度なら冷たい飲み物などを持っていくのにいいと思います。
楽天
|

クーラーボックス
楽天
|
|

カメラ三脚
楽天
|
山で本格的な写真を撮ったり、自画撮りをするときには三脚がいります。
右写真のものは脚が曲がり、木や手すりなどにしばりつけることができるなど、通常の三脚とは違ったカメラの設置が可能なタイプのものです。
今はセルカ棒にスマホをつけて自撮りする若い人もちらほら見られるようになってきました。
|

くねくね三脚:ゴリラポッド
|
|
|
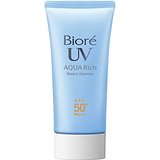
日焼け止め
楽天
|
山登りに行くということは、紫外線を浴びに行くということに他なりません。特に日焼けしたくない女性の方などには必需品かと思います。男性も日焼けはしないに越したことはありません。私は基本的に毎度塗って行きます。
日焼け止めを効果的にするコツは、「ケチらずたっぷり塗ること」です。
|
|

サングラス
|
これもやはり紫外線対策や日焼け予防として。
私は景色をそのままの色で楽しみたいので、サングラスは色の薄いものを愛用しています。
楽天
|

ヘルメット
|
岩山などの険しいルートが予定されているのであれば、ヘルメットがあると安心です。実際、岩場などからの転落事故において生死を分けるのはヘルメット着用の有無であることが多いようです。万が一にも、備えあれば憂いなしです。
アマゾン 楽天 |
|

軽アイゼン
|
冬山はもちろんのこと、夏山でも雪渓歩きがコースにある場合には、あると便利な用具です。軽アイゼン(簡易アイゼン)ということであれば、4本爪か6本爪の物を。
日本三大雪渓といえば、白馬大雪渓、針ノ木雪渓、剱沢雪渓ですね。そういうところに行くのであれば、持って行くのもいいと思います。
 アイゼン・軽アイゼンのメーカーリストはこちらです。 アイゼン・軽アイゼンのメーカーリストはこちらです。
|
|

ネックウォーマーなど
|
冬の里山トレッキングには重宝します。寒風を防いでくれるでしょう。これを装備するとしないとでは、体感温度がまったく違います。マフラーやストールも、おしゃれなアイテムではあります。
ネックウォーマーが活躍したのは、九鬼山。
|
|

携帯カイロ
|
こちらも冬の山歩きのお供の定番。寒い中ではこの暖かさが身にしみるんですよね。
楽天
|
|

 コンドロイチン コンドロイチン
&グルコサミン
|
山歩きをしていると途中からヒザなどが痛くなってしまう方、また、日頃でもヒザの痛みを抱えておられる方はいらっしゃいませんか?(生島ヒロシみたいだな)
私も長く山を歩くとヒザが痛くなることがあったり、それが更には日常も痛くなってしまうことがありました。
そのときに飲んだのが左写真の、野口医学研究所のコンドロイチン&グルコサミン。飲み始めて数日で痛みはなくなり、1瓶30日飲んだあとは、半年ほどは痛みを感じることはありませんでした。半年ほど経ったらまたヒザが痛み始めたのでネットで注文して飲んだら、また数日で痛みはなくなりました。私は上記の商品を長年に渡りヒザの調子が悪くなると飲んでいますが、同様の商品でもよいのではと思います。
こういうものは個人差もあると思いますが、気になる方はそれほど高いものでもないですし、試してみる価値はあると思います。
|